
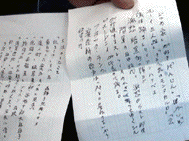

紀行文 岡山映画祭スタッフ 小西 稔子
文中、みどり文字は編集者注となります
8月5日(土曜日)
夏休みの家族連れでごった返す岡山駅。午前10時。
姪御さん(美紀さん)の息子さんである優君(高3)に手を引かれ、松田完一さんが駅に到着された。茶色のポロシャツにモスグリーンの帽子。
東京行きの同行者は、松田完一さん、美紀さんのご家族3人、インタビュアーの中原さん、撮影の大西さん、そして記録の小西。一足先に上京されている代表の小川さんとは現地で合流する予定。いよいよ、一人の市民として映画を観続けた80年の証言『映画の記憶』東京上映へと出発する。手土産に、急遽、「大手饅頭」を50個手配。お客さんに岡山のお土産としてもってかえっていただくためだ。
岡山映画祭から生まれた記録映画が、東京でどのように受け入れられることになるのだろうか。キビ団子ならぬ、大手饅頭をぶらさげ、いざ東京へ。
 |
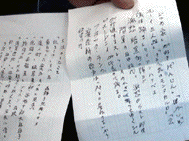 |
 |
車中では、さっそく、インタビュアーの中原さんと松田さんのトークの打ち合わせがはじまる。
(中央写真はトークのために松田さん御自身が書き出された映画のタイトル。実に多岐に渡っていました)
映画の話が始まると、なんとも饒舌になられる松田さん。松田さんの血管はフイルムでできているのだ、ということをあらためて実感。
私と同行の美紀さんとは、もっぱらお昼に何を食べるか、ガイドブックと向き合う。その後は、美紀さんが計画されている、岡山映画資料館の計画の話でもりあがることとなった。
|
|
|
お昼には「たいめいけん」で「伊丹十三風たんぽぽオムライス」を食べる。食欲旺盛でグルメな松田さん。映画とおいしい食べ物が、松田さんのエネルギー源だそうだ。
右写真は「たいめいけん」へ向かうため階段を登る松田さん。この日東京は暑かった。
そして、タクシーで渋谷にある上映会場『UPLINK』へ。気さくな運転手さんに「今日は東京見物ですか?」と聞かれる。お上りさんだと思われたのだろう。そこですかさず「映画の上映に来たんです。運転手さんもぜひ観に来てください」とチラシを手渡し、情宣活動を忘れない。
|
|
|
会場であるUPLINKは、カフェと映画館が隣接する、アンティークでホットな場所だった。
 |
 |
|
アイスティーをのみながら、打ち合わせや資料の用意。以前岡山映画祭に関わり、現在は東京在住のスタッフも数人来てくれて、受付を手伝ってくれたのは心強かった。さすがもと映画祭のスタッフは動き方が違う。ポスターを入り口に張り、あとはお客さんを待つのみとなった。
|
|
 |
 |
一人、二人とお客さんが汗を拭き拭きやってこられる。それが10人ほどになり、あれよあれよというまに60名近い方で会場は埋まってしまった。緑のチラシを持って現れる方、インターネットで見たという方など。ここまで反響があるとは正直思わなかった。
中央写真、男性スタッフの左下には岡山名物「大手まんじゅう」の箱が。松田さんの家の近所にあるこのお店は、「大一」(松田さんの生家)でご飯を食べて、大手まんじゅうを土産に買って帰らないと岡山にいった事にはならないと言われました・・・と松田さんが教えてくださいました。
中原さんのあいさつで、映画が始まる。「岡山以外の場所での上映は今日がはじめてです。お客さんがだれもいなかったらどうしよう、と思っていたのですが、こんなにたくさんの方に来ていただいて、ありがとうございます」と中原さん。
上映後は松田完一さん、聞き手の中原省五さん、日本大学芸術学部教授の田島良一さん、無声映画のピアノ伴奏をされる柳下美恵さんの4人をお迎えしてのトークの時間となる。
中央写真 松田さん所有の「商船テナシティ」のポスターを見せながら、女優について語るお二人。
右写真は大正時代の「尾上松之助」のポスター。このページ一番最後に正面画像を掲載します。
|
|
 |
 |
田島氏の次のような言葉が印象に残っている。
「すばらしい映画をリアルタイムで観られている松田さんがうらやましい。いまではほとんど残っているものがありませんから」
「冷たいリアリズム。人生をそのまま見せるだけ。答えは観客に任せられる。溝口健二の映画はそういう作りになっている。松田さんが一番お好きな映画が溝口健二の『浪花恋歌』だとお聞きして、松田さんの物事への向き合いかたと通じるものがあるのではないか、と思いました」
|
|
|
午後6時半からスターし、大盛況のうちに終わった上映会とトークも9時前には幕を閉じる。その余韻もさめやらぬままに、懇親会の会場へと移動となった。
松田さんは、少しお疲れのようでもあったが「こんなにたくさんの方に来ていただいて、うれしいことです。帰りたくないような気持ちです」と満面の笑みを浮かべておられた。参加者はトークのゲストの方々、岡山出身の映画監督、大学の教授、岡山で自主上映をはじめ、現在東京でもこつこつと上映を続けているという若者、現在東京在住のもと岡山映画祭のスタッフなど、十数名。そこで、映画の感想などが語られた。
「ただの映画史だけでなく、そこに松田さんの一市民としての生き様が重なって見えた」
「好きなことをとにかくやってこられた人生。そういう人生もありだと思えた」
そんな感想が聞こえてきた。
会も終わりに近づいてきたころ、以前岡山大学の講師であり、映画監督をされたこともある福間健二さんから次のような発言があった。
「最後のクレジットで『監督』の明記がなかったけど、それはどうして? 『映画』が生まれ、それが世の中に歩み始めていくとき、映画もひとつの人格としての側面が生まれてくる。そのときに最終的に矢面に立つ人、賞賛も批判も受けて立つ人が必要。それはこの映画に対して一番熱い思いを持つ人でもあると思う。映画をみんなで作る、ということは当然のことで、すべてやらないと監督といえない、ということはないのだから。やっぱり責任を負う人をきちんと立てる、ということは映画が作品となるときには必要なんじゃないの」
そこで、この映画のひとつの特色がたち現れてきたように思えた。
岡山映画祭の代表である小川さんがあたためてこられたこの『映画の記憶』の企画。松田さんという映画とともに生きてこられた人生そのものを、ぜひ残しておかなければ大きな損失になる、そんな思いからのスタートだった。そのインタビュアーを引き受けられ、今回の映画作りの柱となったのは映画祭スタッフの中原さん。中原さんが生きてこられたこれまでが土台となってでてくる問いの数々が、松田さんからさまざまな言葉を引き出していった。今回の映画制作のために費やした時間とエネルギーはそうとうなものだったのだろう。その時間とエネルギーについていえば、カメラを通してその現場を見続け、それを1時間という枠に編集し、音を重ね、『映画の記憶』という作品に仕上げた、大西さんのなされた仕事の大きさも見逃すわけにはいかない。
そして何より今回この映画の製作にあたったお二人は、不思議な信頼関係で結ばれている。大西さんは「中原さんが聞きたいことを聞いてほしい、というのが自分の願いでもあった」と言い、中原さんは「大西さんがやりたいように作ってほしいと思った」と言う。そのうしろでは常に二人と作品を見守る小川さんの視線があり、映画祭スタッフたちの応援があった。これは、今までにない、新しい映画の作り方、映画の誕生の仕方でもあるのではないか。
ただ、福間さんがおっしゃったことは、この映画に一本の柱のようなものをしっかりと立て、作品として世の中にでていくときに、その風を受けて立つ帆をちゃんと立てる必要があるんじゃないの、という暖かいメッセージだったのだと感じていた。
そのことは結論のつかないまま、みなさんからのたくさんの応援メッセージをいただいた懇親会はお開きとなる。そのあと映画祭スタッフで新宿ゴールデン街の寿司屋へ移動。そこで、ぽつぽつと話がはじまった。「この映画の弱さ」という言葉が中原さんから出ていた。「監督とは、その映画から立ち上ってくる匂いがだれのものなのか、ということなのだと思う」とも。この『映画の記憶』という作品からは、どんな匂いが立ち上ってくるのか。それはだれのものだと思えるものなのか。その匂いはどんな人格を持っているのだろうか。
この映画の「弱さ」というのは、もしかしたらそのあたりにあるのかもしれない。その匂いが特定できない、ということに。そして、映画が「作品になる」ということはどういうことなのだろう、ということを考えた。それは、映像、音楽、せりふ、ストーリーというものの、その背後から「何か、独自の魅惑的な匂いが立ち上ってくるかどうか」ということなのかもしれない。
8月6日(日)
上映会の翌日、東京国立近代美術館フイルムセンターに向う。
松田さんは、お持ちの貴重なフイルムやポスターなどの資料を、考え抜いた末、広島市「映像文化ライブラリー」に寄贈された。そのうちの何本かは、ここ東京のフイルムセンターにも新たに収蔵されている。岡山で保存ができなかったことはほんとうに残念なことだが、現在の状況では、岡山では受け皿が用意できなかったのだ。
|
|
|
|
主任研究官の栩木(とちぎ)さんにお話を伺うことができた。
「自分達が楽しんできたものを、次の時代に伝えないで、自分たちだけで消費してしまう、ということは罪なことですよね」とお話されたのが印象的だった。そこで姪御さんの美紀さんから、「岡山でも貴重な資料を残していける、映画資料館を作っていくのが自分たちの使命なんです」という熱い思いが語られた。
「行政の予算で箱を作ってそのなかで仕事をする私たちと、自分の生まれ育った土地で、作品を残していく、いつでも足を運べる場所に箱を作っていく、という松田さんたちの仕事は別のものだけど、いっしょに助け合いながら、学び合いながら、なにかできていくといいですね」そんな栩木さんの言葉があった。「次の時代のために、私には何ができるだろう」という問いを持って、岡山への帰路につくことになった。
松田さんとこのようにごいっしょさせていただく機会も、そうめったにないことだろう。
二日間の時間があっという間でもあり、またずいぶんたくさんの時間が過ぎたようでもあり、密度の濃い時間だったのだと振り返る。
みなさんお疲れさまでした。そして、ありがとうございました。
写真集写真・小西稔子、IKKO
|
|
松田さん所有の「尾上松之助」のポスター