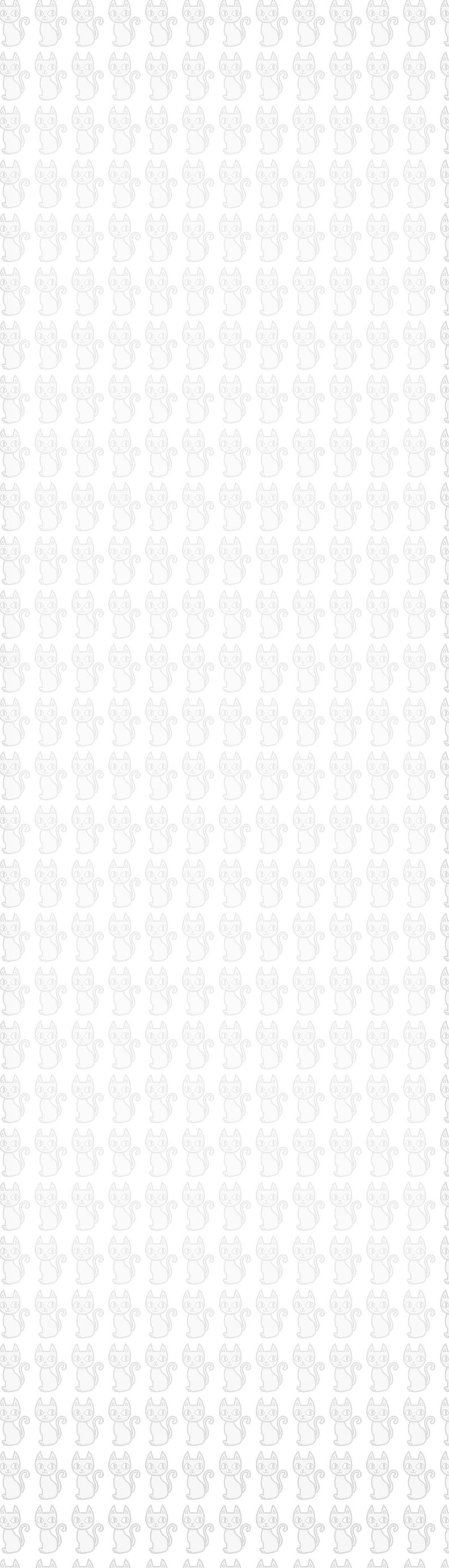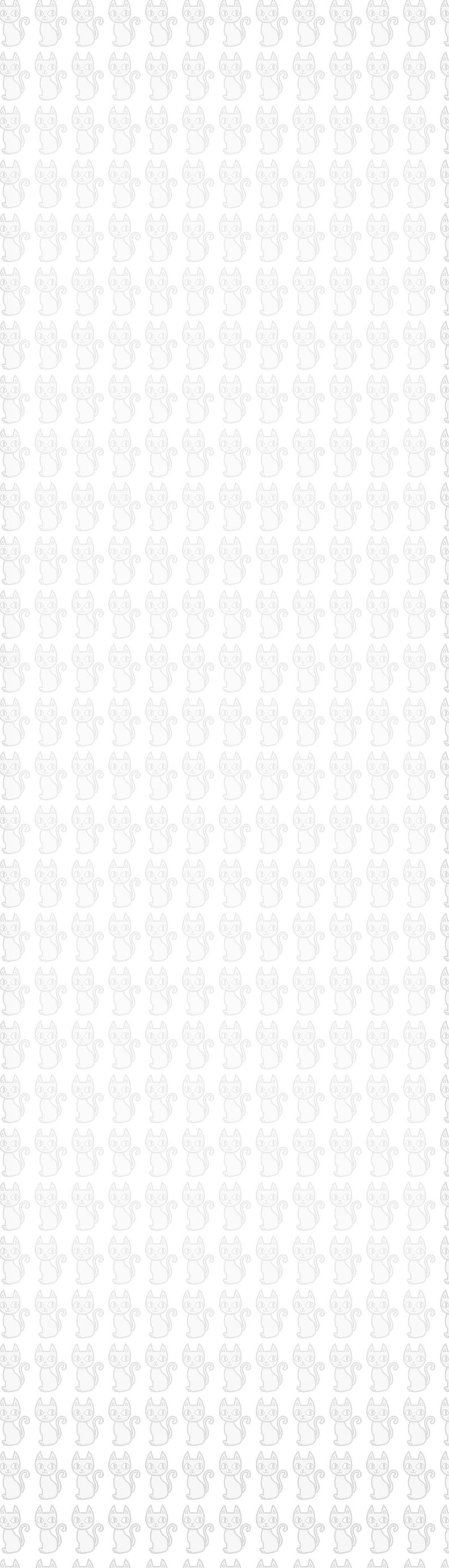約束
1.想いと願いと
あの日々から数ヶ月。
動乱のあけた帝都には多少の平穏が訪れていたが、帝都に、人々に残った傷は大きく深かった。
しかし、そんな中でも立ち上がり歩もうとする者達がいる。
少しづつ、一歩づつ、強く確実に。
帝都極東にあるファランジュ地区、その一角に貴族の居住区があった。
立ち並ぶ屋敷の一つで、その屋敷の主、アドルフ・アルファードは一大決心を前に幾分緊張していた。
『ふう…』
ため息一つ。
そして、彼のいる執務室の扉の向こう側に声を掛ける。
「シンディ、居るか?」
扉が音もなく開き、長い黒髪の女性が一礼して入ってくる。
「お呼びですか、アドルフ様」
「ああ、実はな、パーティーを開こうと思うんだ」
「パーティーですか?」
「ごく身内だけのだがな。
急で悪いんだが、一週間後で大丈夫か?」
「わかりました、早速手配します」
「頼む」
一礼して退出しようとするシンディ、しかしそれをアドルフが呼び止めた。
「えーと、それでだ……。
どうだ、今度のパーティーにあわせてドレスを新調してみないか?」
「私の……ですか?」
アドルフがうんうん、と頷く。
「いえ、私は……」
「まあそう言いつつ、ホントはもう仕立ててあるんだがな」
照れたように笑うアドルフは席を立ち、奥の部屋へと続く扉を開けるとシンディを招き入れた。
「………!?」
いつもは何事にも動じない彼女だったが、その時は一瞬身体をこわばらせた。
そこには純白のドレスがキラキラと輝いていた。
「アドルフ様……これは……」
「知らないのか?ウェディングドレスというやつだ」
「いえ、そうではなくて……」
言葉を続けようとするシンディを遮るように、アドルフが小さな箱を差し出す。
中では静かに光る指輪があった。
「シンディ、私の妻になってくれ」
少し緊張したような声、しかしその言葉には本気があった。
「私は良い主(オーナー)ではなかった、いつもお前に無理をさせている。
だが、これからは私もお前を支えたい。
私の後ろではなく、左の席に居てほしい……」
互いの視線が交わる。
アドルフの素直な眼差し、シンディの戸惑いの瞳。
負けたのはシンディだった。
「……わ…」
喜びと、惑いと、悲しみの入り交じった瞳。
「ダメ……か?」
アドルフの言葉に、シンディが声を絞り出す。
「私は……」
「私は人ではありません。
子をなすことも、ともに老いることさえできません」
「わかっている。
お前はスレイヴ・ドールなのだから当たり前だ。
そんなことを気にしているのか?」
アルファード家当主であるアドルフには、一族の後継を残す義務がある。
そして人とスレイヴ・ドール。
外見は同じでも、スレイヴ・ドールは造られた存在でしかない。
「…………」
しばし無言で俯いていたシンディが、手袋を脱ぎその手のひらをアドルフの前にかざす。
彼女は常に長手袋を着用している。
生命を殺めてきた両の手を隠すように……。
「この手は……血に汚れています。
私はこれまでの戦いで多くの敵を倒してきました」
かざした手を強く握りしめる。
「この手に、その指輪はキレイ過ぎます……」
力無くおろされる腕、依然顔は伏せられたままだ。
マントを広げ、一礼したアドルフが片膝をつく。
諭すような微笑みでシンディを見上げ、そして彼女の手をとり甲に軽く口付ける。
「かまわないさ、私のために戦ってくれたのだろ?
それな……」
俯いたまま、シンディが頭を横に振る。
垂れ落ちた黒髪が顔を隠し、その黒髪の向こうから、落ちる……涙。
「私は……かまいます」
「なぜ?」
『え?』
驚き、困惑するシンディ。
大粒の涙が頬を伝う。
おそらく、彼女が初めて見せたであろう弱さ。
それをアドルフの優しい笑顔が包み込む。
そして、また同じ問い。
「なぜ?」
『何故だろう……』
これまで、シンディは常にアドルフの意に従っていた。
それが彼女の存在の証だったから。
主にすべてを尽くすスレイヴ・ドールとして。
でも、今回は違う。
アドルフは「かまわない」と言った。
シンディは「かまう」と言った。
………………。
初めて主の言葉を拒否し、流した涙の意味。
『好きだから』
そう。
『だから迷惑をかけたくなかった、困らせたくなかった、そして……必要とされたかった』
スレイヴ・ドールを妻に娶ることは、親族の反対はもちろん、周囲も奇異の目でしか見ないだろう。
しかしアドルフにしてみれば、そんなことはどうでもよかった。
スレイヴ・ドールを人としてではなく、スレイヴ・ドールであることを理解し、受け入れ、シンディ・クライムを愛したのだから。
「なぜ……だ?」
三度、その言葉を紡ぐ。
「私が自分から目をそらしていたから……。
そして、アドルフ様が好きだから……」
ぎこちない、精一杯の笑みでアドルフを見つめる。
「私はアドルフ様のことが好きです。
いつまでも、お側にありたいと思います。
それは、この身に過ぎた願いなのでしょうか?」
「お前の願いは私の願いだ。
お前が望むなら、どんな望みも私が叶えてやる。
一緒に居たいというなら、イヤと言うまで居てやるぞ」
溢れ落ちる涙が量を増す。
でも、それは暖かい喜びの涙。
「名を、アルファードの名を私にください……」
「アドルフ様は私の存在理由、絶対正義。
私があのお方の側にいることに理由など無い」
あの日、言った言葉。
そう、理由など無い。
必要ない。
互いの想いさえあれば……。

【Stellamaris Saga】の後日談です。
当時から考えていたので、構想数年の大作!?(苦笑)
“1.”とあるように、さらに後があるのですが……いつ書かれるかは不明(汗)
シンディも、人間みたくなってきたなあ……。