第2章多回給飼のための牛舎改造
どうすれば牛がうまく飼えるのかーー日々そのことを模索していました。二本立て給与法、NRC、日本飼養標準など、エサの勉強もずいぶんしました。
そうこうしながら昭和54年頃、誰から教わったわけでもなく、経験的“多回給飼”が一つのポイントであることを知りました。当時、コンピュータで瞬時に飼料計算ができるようになって、数字的には簡単に答えが出てくるようになりましたが、それよりも多回給飼を大事にすることのほうが牛の調子は良かったのです。濃厚飼料は1日7〜8回に分けて給与していました。コーンサイレージや乾草の自給飼料も給与していました。本当に牛の調子は良くなり、6500kgくらいだった平均乳量が8500kgになりました。そうして自信を持てるようになったのですが、生身の人間が1日8回もエサ給与するのは無理でした。体力的にみて、とても長続きするものではなかったのです。
そこで昭和58年頃、当時はまだめずらしかったフリーストールに興味を持つようになり、自分もやってみようと思いました。しかし、まだ経営的には立ち直ってないので、お金も貸してもらえず、結局、19頭繋ぎの牛舎の中で牛を繋がずに自由に歩けるように改造しました。なるほど省力化されてうまくいったのですが、反対に向いて寝る牛がいたり、通路で寝る牛がいたりして牛が汚れたのにはまいりました。
そこで、今度は図1のように改造しました。新たに飼槽を作って、そこでエサを食べられるようにしました。外にはホールディングエリアを作り、搾乳のときには4頭分のパイプラインミルカーで搾るようにしました。3回搾乳もしました、これは結構うまくいき、3年間くらい続けました。平均乳量は1万500〜1万800kgでした。しかし、今まで繋いでいた牛をフリーストールに入れたこともあり、大半の牛は肢がダメになってしまいました。ですからその3年間は、経営的には儲かったとまではいきませんでしたが、貴重な経験ができました。その経験が、その後の役にたったのです。
当時の酪農は景気が良く、雄仔牛は12〜13万円、老廃牛も30〜40万円でした。みなさんは儲けていたと思いますが、私はこのようなことばかりしていたので、ちっとも儲からなかったのです。経営は一番きつかった反面、一番勉強したり経験した時期でした。そして、コストダウンのコツをつかんだ時期でもありました。
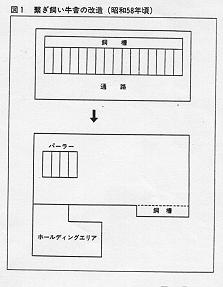 図1繋ぎ飼い牛舎の改造(昭和58年頃)
図1繋ぎ飼い牛舎の改造(昭和58年頃)